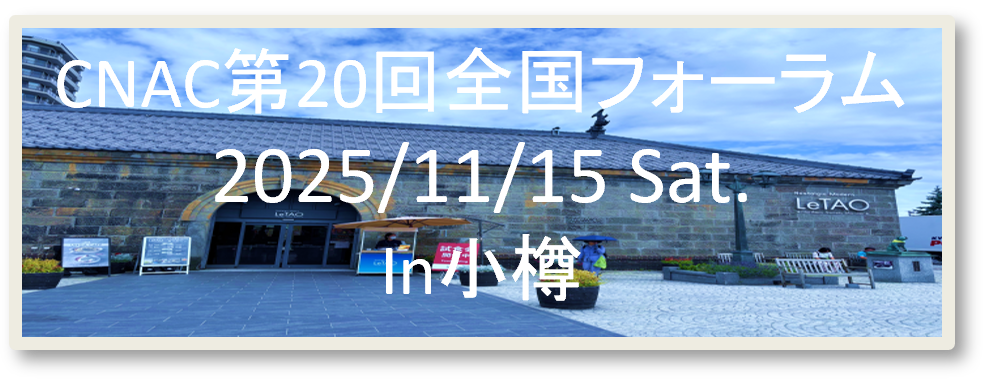第227号「酷暑に対応した海辺の体験活動を構築しましょう」2025.8.29配信
今年の夏も酷い暑さですね。しかし、暑い夏には、水辺で涼むというのは、今は昔の話しなのでしょうか。「危険な暑さです。不要不急の外出は控えましょう」というフレーズの熱中症警戒アラートで、遊びに外に出ることが憚られるような情報発信が国から行われているのを見ると、なんだか切なくなります。せめて、不要不急という文言は外してほしいと思うのは、私だけでしょうか?野外でからこそ、涼しく過ごせる場所や時間があるんですが・・・。きちんと調査したわけではありませんが、私の周りのカヌーやカヤック、SUPなどのパドルスポーツアクティビティの提供事業者の多くが、本来稼ぎ時である夏場の予約減少に直面しているようです。酷暑で海水浴場の人出が減っているというニュースも目にします。
趣味の多様化や、アクティビティ提供事業者の増加も原因かもしれませんが、酷暑とそれに伴う様々な情報発信や、社会の雰囲気の影響が大きいのではないかと考えてしまいます。
私が育った宮城県女川町の漁村では、夏の暑い日は小舟で小さな磯浜に出かけ、家族で海水浴を楽しむのが恒例行事でした。おおらかな時代で、海水浴=ウニやアワビを採っただけ食べられる、今考えると非常に贅沢な海水浴でした。(当時は、泳ぎに行ってその場で食べるぐらいの密漁が社会的に許容されていました。)アルミホイルに包んだジャガイモをたき火に放り込んで、大人も子どもも海に入り、ウニやアワビを採って、たき火で焼いて食べる。普段はウニを食べない(当時は、夏のウニ漁が盛んで、夏の食卓にウニがあるのが日常でした。そして、子どもには美味しくない食べ物の一つだったのです。)子どもだった私も、このときばかりはたき火で焼かれた香ばしい焼ウニを、ジャガイモと共にバクバク食べるのでした。
そんな海に30分も入っていると、唇が紫色になり、凍えてくるので、日向で焚き火に当たって温まりながら海水浴を楽しんでいました。あまり遡って調べられなかったのですが、2013年8月の宮城県女川町沿岸の海面水温は、23℃で、今よりも2℃ほど低かったようです。私が海水浴に家族で出かけていたのは、1980年代後半です。
私がたき火の仕方を教えてもらったのも、岩に足をぶつけてざっくり切って、応急手当を初めて学んだのもそんな海水浴の時でした。私のアウトドア活動の原点は夏の海水浴でした。そんな夏の海が「酷暑」を理由に敬遠されているのなら、酷暑の夏も海辺で安全に楽しく過ごせる方法の研究や、酷暑の中でも安全かつ快適な活動ができるプログラムの開発、それらをサポートする器材の研究など、「酷暑」に対応した海辺の体験活動を積極的に構築しなければいけない状況になったことを改めて実感した夏となりました。課題は山積みで、解決はとても難しそうですが、来年の夏に向けて、どんどん動いていきたいと思います。
一般社団法人セーフティパドリング協会 事務局長 紺野祐樹
https://japan-safe-paddling.org/
2025年8月25日|キーワード:体験、海