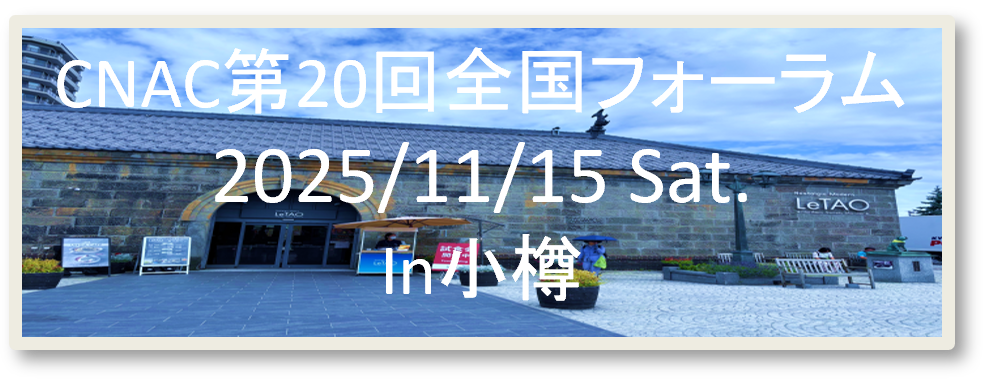第221号「海ののぞき窓」2025.2.28配信
6年前に東伊豆に引っ越しました。アパートは徒歩10分で海に出ます。海岸にはタイドプールがあり、大きさは15m四方くらい、深さは最大3m、潮溜まりと言うと大きすぎるので、タイドプールという呼び名がピッタリです。海につながる水路があったり、棚があったり、根があったり、亀裂も多く入っていて変化があります。入ってみると、メジナの若魚がたくさん群れていて、サンゴも付いています。なんと6種類。潮が引いている時は、外海の波は入ってこないので、水面は鏡のよう、まさにプールです。 引っ越して、新しい環境や仕事に慣れる合間の水遊び、という感じで楽しんでいました。秋になり水温が下がり、足は遠のいてしまいました。2年目のGW明け、久しぶりにタイドプールに行ってみると、ホンダワラ類の海藻が、ジャングルのように茂っていてビックリ!そこからタイドプール通いが始まりました。目標は月に4回・週1回のペース。 様々な環境があることもあり、魚、エビ、カニ、ヤドカリ、巻貝、ウニ、ヒトデ、ナマコなど、たくさんの生き物に出会えます。いつも会えるものもいれば、出会っても次には姿が見えないものもいます。夏から秋にかけては、魚たちの季節。常連は、メジナ・ギンユゴイ・ベラ達・スズメダイ達とカエルウオ。時々アジやサバが入ってきます。1度だけですが、ダツやカンパチ、マグロの子どもが入ったこともあります。南で生まれて、黒潮に乗ってやってくる季節来遊魚たちも毎年やってきます。チョウハンなどのチョウチョウウオの仲間たちやスズメダイの仲間たちなど。私が毎年楽しみにしているのが、サザナミヤッコの幼魚。毎年数尾はやってきますが、冬になると力尽きていなくなってしまいます。ウツボもほぼ常駐状態なので、餌になってしまうのでしょう。2023年は長く生き延びて、翌年のGWまでいたので、越冬に成功したのかと思いましたが、GW明けには姿を消してしまいました。
冬から春にかけて、水温が下がる時期は、海藻の季節。陸上の植物は寒い冬が苦手ですが、海中の海藻は冷たい時期が得意です。大きなコンブ類は北海道の海に暮らしていて、沖縄のサンゴ礁には大型の海藻は育ちません。ここでは、アカモク・イソモク・ヤツマタモクというホンダワラの仲間が繁茂します。茎は細くしなやかで、波がきても揺れて力を逃がし、長く成長します。葉の間には、果実のような丸いもの(気胞)がついて、つぶしてみるとプクッとガスが出てきます。この気胞の浮力で、水面に向かって立ち上がり、太陽光を受けて光合成をおこないます。GW頃には、水面まで伸びて水面を覆うようになり、まるでジャングルのようです。海藻が絡みついて、泳ぐのが大変です。この頃には、幼魚が増えて、夏とはまったく違う世界を作っています。
海藻の楽しみがもう一つあります。晴れていて、潮が低く外海の波が入らない鏡のような水面の昼頃、ホンダワラの藻体全体が銀色に輝いて見えることです。銀色の正体は、小さな気泡。太陽光を全身に浴びて、せっせと行った光合成でできた酸素の気泡。この気泡が藻体から離れずに全身が銀色に輝くのです。今まで水中で色々な景色を見てきましたが、この光景は見たことがありません。外海では、波や流れがあり海水は常に動いているため、光合成でできた小さな気泡は、すぐに藻体から離れてしまうからでしょう。皆さんにも見ていただきたいのですが、水温が低すぎて、安易にはお勧めできないのが残念です。
このタイドプールに来ているのは、私だけではありません。一年中見かけるのは、釣りの方々。釣り竿はタイドプールにではなく、外海に向けて釣っています。釣果を入れた網をタイドプールに吊るしているので、覗いてみると、大きなブダイ、メジナ、イシダイなどが釣れています。その場で頭を落として内臓をタイドプールに捨てていく人も。私は、ちょっと残念な気分になってしまいますが、タイドプールの生き物たちには、「棚から牡丹餅」状態なのでしょう。巻貝やヤドカリが集まっています。夏には海あそびの家族連れが、浮き輪で浮かんでいます。スノーケリングで水中を覗く子どももちらほら、お父さんやお母さんは、ダイビングの経験があるようです。外海は深いし、波もあるし、安心して海を楽しむいい環境です。みんな楽しそうです。おっと、サンゴを踏んでいる人も、でもサンゴには大したダメージはないようです。サンゴが生きていることに気付いてもらいたいものです。秋には、大きな網を持って、熱帯魚の子どもたちをすくう人もやってきます。成長を見守っている私には、とても残念ですが、いずれ死んでしまう子たち、おうちの水槽で大事に育てられるのもいいのかも。海との距離が近くなることはいいことですからね。 タイドプールは、大きな海の小さなのぞき窓のようです。いろいろな人が海とのかかわりの入り口として使っているようです。定点観察を続けること5年。新しい発見や「どうしてなの」という疑問がどんどん増えていきます。自然の奥行きは、とてもとても深いもの、この楽しみはやめられません。
CNAC理事/NPO法人国際自然大学校(NOTS) 檀野清司
https://www.nots.gr.jp/
2025年2月14日|キーワード:自然、生き物