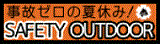第204号「ある夏の思い出~海の怪談~」2023.9.29配信
世の中の一般家庭には未だ冷蔵庫もクラーも無く、電気器具と言えば、六畳間の裸電球と古びたラジオと母の嫁入り道具であった電気アイロンくらいの生活が私の子供時代であった。夏になって涼をとる手段と言えば、家中の窓を開け放ち、蚊帳を吊り、団扇を使いながらラジオから流れる怪談話に耳を傾けて早々に寝るという、今から思えば何とも長閑で健康的な暮らしであった。
とある夏、ラジオから流れる話に妙に引き込まれ、いつもなら途中で寝てしまうのに、なぜか最後の落ちまで聞いてしまった。今から思い出すと、それは千石船が活躍した時代の実話とも物語とも区別がつかぬ、何とも怖い話であった。
その若者が水夫見習いとして船で奉公働きを始めて間もないころの出来事であった。昼間の穏やかな空模様が夕方になるに連れて、怪しい雲行きとなり、次第に雨風は激しさを増し、遂には老練な先輩水夫たちや船頭も船に打ち込む波との格闘に疲れ果て、いよいよ帆柱を切り倒し流されるに任せるしかないと叫び交わし始めたころ、天の助けか、岸に微かな明かりを見つけ、船頭は最後の力を振り絞って船の舳先をその明かりに向けて舵を切った。
若者が気付いたのは、品の良さそうな人々が心配そうにのぞき込む目であった。その中で村の長と思しき人物がおもむろに「どこから来なさった?」と尋ねた。若者は何ごとかを答えようとしたが口をついて出たのは「え~」とも「う~」ともつかない呻きにも近いつぶやきであった。何事かを思い出そうとするのだが、一体自分が何者でどこから来て何をしに何処へ行こうとしていたのかさっぱり頭に浮かばないのであった。その様子を見た村の長は「これなら良いだろう」と皆の衆を見渡しながら言い渡した。
若者が気付くまでの間、幾日横たわっていたのか想像するしかなかったが、かいがいしく身の回りの世話をしてくれる若い娘の話の端々から推察するに少なくとも数か月は意識を失っていたようであった。
次第に体力も回復し、その村の暮らし振りにも関心が向くようになったころ、人々の話しぶりに京訛りが聞き取れ、たいした田畑も無いのに結構豊かな暮らし振りであり、海が目の前にあるのに漁をしている様子も無かった。娘の話を繋ぎ合わせて理解できたのは、村の長の蔵には先祖代々の宝物があり、それを時々大人たちが京に運んでは村の暮らしに必要な物を仕入れてくると言う事、海には「亀様」と呼ばれる神がおり、海辺の寒村を海の猛威から守っていると同時に海から宝物を運んで来るとのことであった。
若者は自分が何者であるかを思い出せないまま、平穏な日々が過ぎ、いつしか身の回りの世話をやいてくれていた娘と所帯を持ち可愛い子供たちにも恵まれていた。
そんなある日、村の長を始めとした主だった大人たちが空を見上げながら「今夜あたりは亀様がお出ましになるかもしれん。」と何事か相談している様子であった。
若者夫婦は日が沈むといつの様に子供たちを寝かしつけ早々に床に就いた。ふと気付くと外は今まで経験したことの無いような暴風雨となっていた。若者は起きだして風で入口の戸板が飛ばないようにと筋交いを嚙ませようと外を見た瞬間、浜で赤々と焚かれている篝火が目に飛び込んできた。そしてその明かりに照らされて、浜の沖には亀様と呼ばれる岩礁が黒々と姿を現していた。
その瞬間、若者は思い出せないでいた自分の記憶がまざまざと目に浮かび、あの船頭の「取り舵~~~」との最後の叫びが今の出来事のように耳に響き、身じろぎも出来ず戸口に立ち尽くした。
その時「行かないで」と囁きつつ、千石船の碇綱のごとき力で娘が若者の手を掴んでいた。
今でも時折、私たちが潮風と潮騒の中に哀愁を認めるのは、等しくこの若者の末裔かもしれないと言う。(終)
α&ω技術士事務所 代表 山根隆行
2023年9月11日|キーワード:海