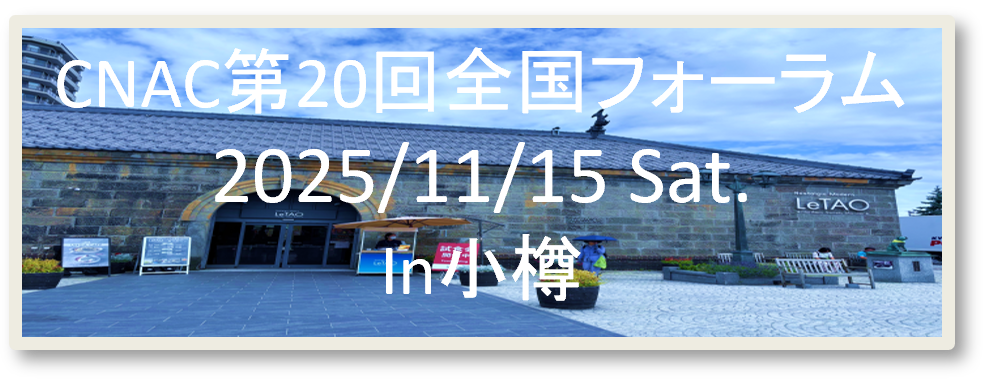第229号「もし水に落ちたら?~“予防”と“防止”で命を守るために~」2025.10.30配信
私の所属するNPO法人・日本安全潜水教育協会(JCUE)では、2007年より水辺の安全活動の一環として“着衣泳”に取り組んでいます。“着衣泳”とは、衣服や靴を身につけたまま浮いて助けを待つという「救助される側」のスキルです。
ダイビングでは、溺者を曳航したり引き上げたりといった「救助する側」の技術が重視されます。ところが、「万が一落水してしまったとき、自分自身で助かる方法がある」と知ったときには〈目からウロコ〉でした。服や靴、体内の空気を利用して仰向けに浮く“背浮き”は、泳がずとも呼吸を確保でき、不意の落水時に命を守る行動となります。
それ以来、主に児童生徒を対象に、学校での講習会や自然観察会などを通じて着衣泳の普及に努めてきました。けれども毎年、水の事故は後を絶ちません。楽しい時間が一瞬で悲劇に変わる――その多くは、ほんの少しの注意で防げるものです。
ここで改めて考えたいのが、「溺れの予防」と「防止」という二つの視点です。
「予防」とは、溺れが起こる前に危険を減らす取り組みのこと。〈子どもへの安全教育〉〈ライフジャケット着用の推進〉〈見守る大人の意識づけ〉などがそれに当たります。これらは、事故を“起こさないための備え”です。
一方、「防止」とは、危険が迫った瞬間に実際の溺れを起こさせない行動を指します。〈着衣泳(背浮き)〉は、まさに“その場で事故を食い止める”力です。
「予防」と「防止」は似ていますが、実は異なる段階の取り組みです。予防は日常の備え、防止は瞬時の判断と行動。どちらも欠かせない意識として、水辺の安全を守る力にしていきたいものです。
自然の中で活動している私たちは、水に親しむ楽しさと同時に、その危険性にも目を向けています。水辺の楽しさと安全は相反するものではなく、少しの知識と備えで両立できるものです。
「予防」と「防止」を意識した行動が、きっと未来の命を守ります。これからも皆さんと一緒に学び合いながら、その大切さを社会や一般の方々にも広め、水辺の安全文化を次の世代へつないでいきたいと思います。
NPO 日本安全潜水教育協会(JCUE)理事 / 早川 弘子
https://jcue.net/
2025年10月23日|キーワード:安全、体験