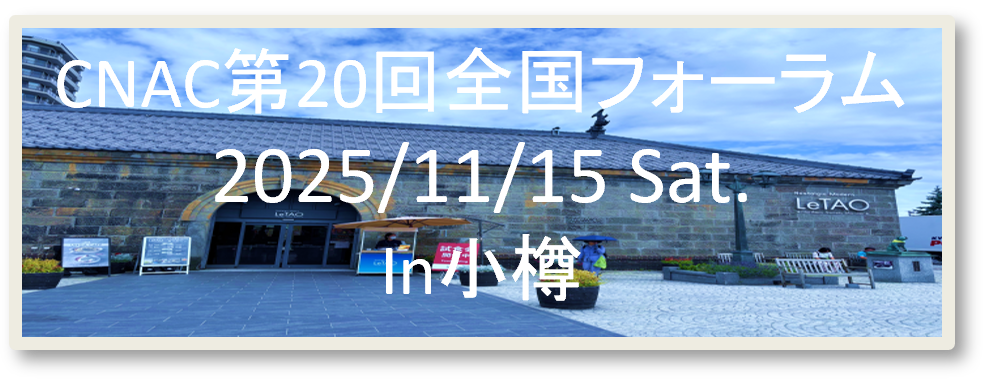第228号「意図的な原体験の創出」2025.9.26配信
「海の原体験はいつですか?」そう問われたらあなたはどう答えますか?私の記憶は7歳ごろ、新潟での海水浴です。浮き輪に入って流されて、なんと泳げない母親が深場まで助けに来ていたのです。とっさに私は浮き輪を抜けて母親に浮き輪を渡しました。とはいえ母親の捕まる浮きを引いて上手に泳げるわけでもなく二人で溺れそうになっているところに知らないおじさんが2人、助けに来てくれて足が付くところまで浮き輪ごと引いて泳いでくれました。これって結構海が嫌いになりそうな原体験ですが、不思議なもので今はCNACの活動に関わり続けています。
さて、日本人の海離れが叫ばれて久しいこの頃ですが、人生で初めて海に入る経験も徐々に高齢化している気がします。私が海辺に引率する児童は5・6年生(11歳‐12歳)が多いのですが、全体の2割から3割が「初めて海に入る」と返答します。厳密には海にはよく行くけど水には入らない、ということが多いようです。
一方で私立の小中学校が海に学習フィールドを求めたり、日本財団の「海と日本プロジェクト」が日本各地で展開されていたりと、私が海辺で教育施設を運営していることもありますが、このような機会の指導依頼も増えてきました。
事前学習で数種類の生き物の生態を学習して、子どもたちは干潮の時間に磯の生き物を採取するわけですが、ここが大変です。そもそも海まで歩く途中の道すがら蝶やハチに驚いて悲鳴を上げる子、海に入るという興奮を抑えられない子、砂や岩の足裏感覚が慣れなくて足元ばかり見る子、磯場の匂いで気持ち悪くなる子、大量のフナムシに固まる子、それぞれの海の経験値が垣間見えます。採取される生きものは、ウニやナマコ、カニ、ヤドカリ、ヒトデ、エビやハゼの仲間たちといったところでしょうか。初めて見るその姿形に興奮し、恐る恐る触り、撫で、つまみじっくりと観察してゆきます。知識をいっぱい持った背伸びした子供たちでも、全身濡らして生き物を目の当たりすると非常に子供らしいリアクションと純粋なまなざしで生き物と向き合っている気がします。なんだかんだ一番盛り上がるのは、みんなで波に乗り、みんなで波に転がされている瞬間です。これからもそんな「海の原体験」の場を作り続けます。
CNAC副代表理事/南房総市大房岬自然の家所長 神保清司
https://taibusa.jp/
2025年9月24日|キーワード:体験、海